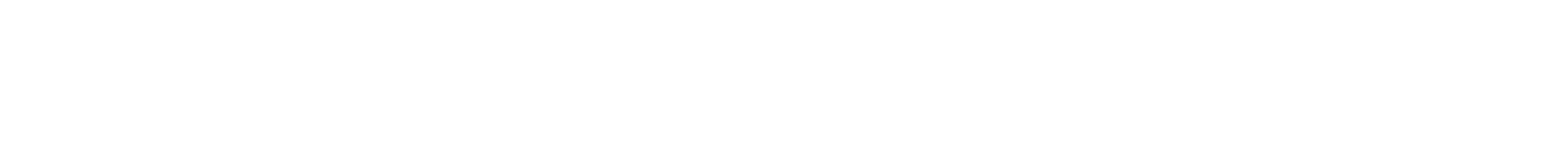随意契約考察 代表理事月報(2025年6月 )
1. 随意契約について
随意契約とは、発注者が特定の業者を選定し、競争入札を経ずに直接契約を結ぶ方式です。本来、公共事業や物品購入などの契約は、透明性や公正性を確保するために競争入札によって行うことが原則とされています。
しかし、一定の条件下では、随意契約が認められており、例えば緊急性が高い場合や、特定の業者でなければ対応ができない場合などが該当します。
随意契約は、地方自治法施行令、財政法、会計法などに基づいて定められており、契約金額や内容に応じて使い分けられています。
また、近年では透明性確保の観点から、随意契約に関する情報の公表も進められています。
2. 農水省古米の随意契約概要
農林水産省では、備蓄米(特に古米)の売却において随意契約を適用する事例があります。たとえば、一定期間備蓄された古米は、一般消費用には適さず、加工用や飼料用などの限定的な用途に限られるため、買い手が限られるのが現状です。
このため、農水省は加工業者や飼料業者など、特定の条件を満たす事業者を対象に、競争入札ではなく随意契約で売却を行ってきました。過去には、業者との取引実績や、加工能力、流通ルートなどを考慮して業者を選定し、一定の価格で契約するという方法が採用されています。
しかし、この古米の随意契約については、不透明さや価格の妥当性に疑問が投げかけられたこともあり、メディアや会計検査院などからの指摘を受けるケースもありました。
3. 随意契約の問題点と課題
随意契約にはいくつかの問題点と課題が存在します。
• 透明性の欠如
競争が行われないため、契約の公正性や価格の適正性が外部から見えにくく、不正や癒着の温床となるリスクがあります。
• 競争原理の欠如
競争が働かないことで、コスト削減のインセンティブが弱まり、結果として市場価格より高い契約になる可能性があります。
• 選定基準の曖昧さ
どの業者が選ばれ、なぜその業者と契約したのかが明確でないケースがあり、行政への信頼を損なう要因となり得ます。
• 情報公開の不十分さ
随意契約の契約内容や選定理由、価格などの情報が十分に公表されていない場合が多く、国民への説明責任が果たされていないとされます。
4. 随意契約の今後について
今後の随意契約の運用においては、以下のような方向性が求められます。
• 情報公開の徹底
随意契約の内容、相手方、契約理由、価格などを積極的に公表し、透明性の確保を図る必要があります。
• 選定プロセスの明確化
なぜ競争ではなく随意契約としたのか、その理由を明文化し、第三者が検証できるようにすることが重要です。
• 監査・評価の強化
契約後の事後評価や監査体制を強化し、不適切な契約があれば早期に是正される仕組みを整備する必要があります。
• 原則として競争契約の徹底
やむを得ない場合を除き、可能な限り一般競争入札または指名競争入札を実施する方向で制度運用の見直しが進むことが望まれます。
今月はここまで
一般社団法人入札総合研究所
青柳 恭弘